※この記事にはPR(広告)が含まれます。
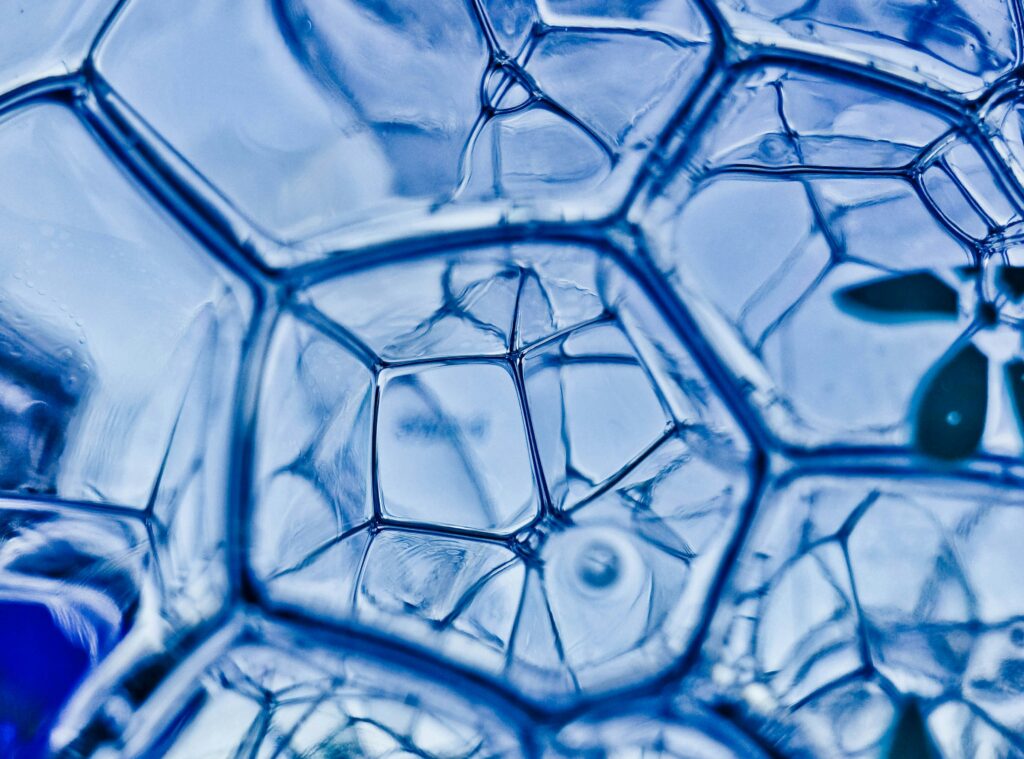
建築士の勉強をしていると、「潜熱」「顕熱」「全熱」という言葉を必ず目にしますよね。
でも、「顕熱(けんねつ)」「全熱(ぜんねつ)」と並ぶと、なんとなくイメージがつきにくい……。
どれも“熱”には違いないのに、「何が違うの?」と感じた経験はありませんか?

実はこの3つの熱の概念は、建物の快適性や省エネ性能を考えるうえで欠かせない基本要素。
たとえば「お風呂上がりに寒くなる理由」や「エアコンの除湿モードが心地よい理由」にも、深く関係しています。
この記事では、難しい数式や理論に立ち入らず、建築と暮らしの両面から“見えない熱の正体”を整理していきます。
この記事を読むことで、試験の知識を「丸暗記」ではなく「納得して使える知識」へと変えることができます。
基本解説|潜熱・顕熱・全熱とは?

建築環境分野の学習を始めると、最初に登場するのが「潜熱(せんねつ)」と「顕熱(けんねつ)」という2つの熱の概念です。
どちらも同じ“熱エネルギー”ですが、その移動の仕方が異なる点が重要です。この違いを理解しておくことは、空調負荷の計算や快適な室内環境の設計に欠かせません。
- 顕熱:温度変化で生じる熱(=目に見える)
- 潜熱:状態変化で生じる熱(=見えない)
- 全熱:それらをまとめた空気の総エネルギー
顕熱(Sensible Heat)=温度変化による熱
顕熱とは、物質の温度が変化することで出入りする熱のことを指します。
たとえば、ストーブで室内の空気を温めるとき。
空気の温度が20℃から25℃に上昇する上昇します。この温度変化による熱が「顕熱」です。
つまり、温度計で測ることができる熱。
“顕(あらわ)になる熱”という言葉のとおり、目に見える温度変化として確認できるのが特徴です。
建築的には、暖房や冷房によって空気の温度を上下させる際に扱うのが顕熱です。
潜熱(Latent Heat)=状態変化による熱
一方で潜熱とは、物質の状態(固体・液体・気体)が変化するときに出入りする熱を指します。
たとえば、水が蒸発して水蒸気になるとき、または逆に水蒸気が冷えて水滴に戻るとき。
この“見えない変化”の裏側では、大きな熱の出入りが発生しています。
このときの熱は温度計には現れません。
つまり、温度が変わらなくても、エネルギーのやりとりがあるというのが潜熱のポイントです。そのため「潜(ひそ)む熱」と呼ばれます。
建築環境では、湿度変化や結露・蒸発など、水分が関わる現象に深く関係します。
冷房や除湿の設計で登場する「潜熱負荷」という言葉は、まさにこの“水分が含む熱”を指しています。
全熱(Total Heat)=顕熱+潜熱
そして「全熱」とは、顕熱と潜熱を合わせた総エネルギーのことです。
空気には「温度(顕熱)」と「湿気(水蒸気=潜熱)」の両方のエネルギーが含まれています。これらをまとめて扱う考え方が“全熱(ぜんねつ)”です。
たとえば、全熱交換器では、排気の「温度」と「湿度」の両方のエネルギーを回収して、外気を効率よく室温に近づける仕組みを実現しています。
つまり、全熱=温度+湿度=空気の持つ総合的なエネルギー。
この考え方が、近年の省エネ建築や高効率空調の設計で欠かせない基礎となっています。
潜熱・顕熱・全熱の違いまとめ
| 種類 | 熱の正体 | 温度変化 | 状態変化 | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 顕熱 | 温度変化に伴う熱 | 〇 | × | 空気を暖める・冷やす |
| 潜熱 | 状態変化に伴う熱 | × | 〇 | 水の蒸発・結露・凍結 |
| 全熱 | 顕熱+潜熱 | 〇 | 〇 | 空調・熱交換器の熱エネルギー |
これら3つの関係を整理しておくと、次に学ぶ「空調負荷」や「全熱交換器」の仕組みがぐっと理解しやすくなります。
とくに潜熱は、数値では見えにくいものの、人の快適さを左右する重要な要素。
温度だけでなく湿度も含めて“熱”をとらえる視点こそが、建築の温熱環境を支える基本です。
建築への応用|空調負荷・熱交換・除湿設計の考え方

潜熱・顕熱・全熱の関係は、空調設計や建築環境工学の中で非常に重要な概念です。
建築の中で「熱」を扱う際には、単に温度(=顕熱)をコントロールするだけでなく、空気中の水分(=潜熱)をどう管理するかが快適性を左右します。
ここでは、それぞれの熱がどのように設計と関わるのかを整理してみましょう。
空調負荷|温度と湿度の「2つの負荷」を考える
室内を快適な温湿度に保つために必要なエネルギー量を「空調負荷」といいます。
この空調負荷は、冷房負荷と暖房負荷に大別され、それぞれ次のように定義されます。
- 冷房負荷:夏期に室内を涼しく保つため、除去すべき熱量
- 暖房負荷:冬期に室内を暖かく保つため、供給すべき熱量
さらに、熱の性質によって以下の2種類に分類されます。
| 種類 | 内容 | 主な要因 |
|---|---|---|
| 顕熱負荷 | 室温を上げ下げするための熱 | 日射・照明・人体・機器など |
| 潜熱負荷 | 湿度を上げ下げするための熱 | 人の呼気・調理・洗濯物・湿気の侵入など |
冷房運転時には、空気の温度を下げるための「顕熱負荷」に加え、空気中の水蒸気を取り除くための「潜熱負荷」が生じます。
特に日本のような高温多湿の気候では、潜熱負荷(=湿度に関わる熱)の割合が大きくなります。
単に温度を下げるだけでは不快感が残るのは、「潜熱」が処理しきれていないからです。
つまり、“快適な空間=顕熱+潜熱のバランス設計”なのです。
熱交換器|「全熱」でエネルギーを無駄にしない
建物では、換気によって新鮮な外気を取り入れるとき、室内の快適な空気も一緒に逃げてしまいます。
その“熱の損失”を減らすために使われるのが、熱交換器(Heat Exchanger)です。
なかでも、省エネ性能が高く快適性にも優れるのが全熱交換器。
排気の中に含まれる温度(顕熱)と湿度(潜熱)の両方を回収し、新鮮な外気を室内の温度・湿度に近づけて取り込む装置です。
| 種類 | 回収する熱 | 特徴 |
|---|---|---|
| 顕熱交換器 | 温度のみ | 湿度は回収しない |
| 全熱交換器 | 温度+湿度 | 省エネ性・快適性が高い |
このように、全熱交換は「温度」と「湿度」のエネルギーを再利用することで、省エネルギーと快適性を両立させる建築技術といえます。
除湿設計と潜熱のコントロール|デシカント空調
除湿とは、空気中の水蒸気を取り除くこと。
つまり、潜熱を取り除く=湿度を下げるということです。
特に日本のように高温多湿な環境では、空気中の水分(=潜熱)をどのように処理するかが快適性と省エネルギーの両面で重要になります。
一般的なエアコンでは、冷却コイルで空気を冷やす際に、コイル表面で水蒸気が凝結し、潜熱が放出されます。
この過程で湿度が下がり、室内はさらっと快適な環境になります。
ただし、この方式では過冷却や再熱といった工程が必要になるため、効率面で課題が残ります。
その代替技術として、デシカント空調(吸湿剤を利用して湿度を制御する方式)もあります。
これは、温度と湿度を分離して制御できる仕組みで、近年では商業施設や高湿度空間などでの採用が進んでいます。
つまり、現代の建築環境設計では「快適さ」だけでなく、「効率」や「省エネ」まで含めた潜熱のマネジメントが、空間の質を左右する要素となっているのです。
試験での出題ポイント|一級建築士試験での頻出分野
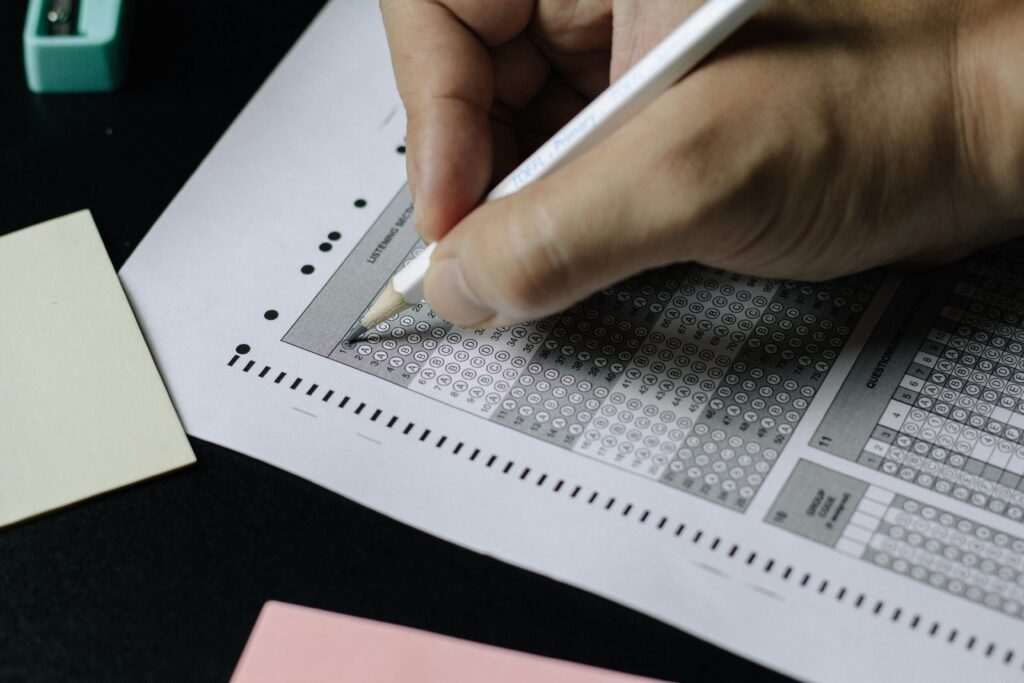
潜熱・顕熱・全熱の概念は、一級建築士試験の「環境・設備」分野で毎年のように問われる重要テーマです。
特に、人体の発熱や空調設備の熱回収に関する出題が多く、「どの熱が増減するのか」を正確に理解しておくことがポイントです。
以下に、過去の代表的な出題例を整理します。
一級建築士試験(H29)環境・設備
室内発熱負荷には、顕熱と潜熱があり、人体に起因する潜熱は、同一作業の場合、室温が高いほど小さくなる。
解答:×
解説:
作業量(代謝量)が同じであれば、室温が高くなるほど人体は体温を逃がすために発汗が増加します。
そのため、顕熱の発熱量は減少し、潜熱(汗による蒸発熱)が増加します。
人体の総発熱量(顕熱+潜熱)はほぼ一定である点を押さえておきましょう。
一級建築士試験(H22)環境・設備
作業の程度に応じて代謝量が増えるにつれて、一般に、人体からの総発熱量に占める顕熱発熱量の比率は増加する。
解答:×
解説:
作業が激しくなるほど代謝量は増加し、体温上昇を防ぐために発汗(=潜熱)が増えます。
したがって、代謝量の増加に伴って顕熱の比率ではなく潜熱の比率が増加します。
一級建築士試験(H30)環境・設備
外気取入れ経路に全熱交換器が設置されている場合、中間期等の外気冷房が効果的な状況においては、一般に、バイパスを設けて熱交換を行わないほうが省エネルギー上有効である。
解答:〇
解説:
中間期など外気温が室温より低く外気冷房が有効なとき、全熱交換器を通すと外気が暖められてしまい、冷房効果が低下します。
したがって、バイパスして熱交換を行わない方が省エネルギー上有効です。
一級建築士試験(R4)環境・設備
潜熱回収型ガス給湯機は、一般に、潜熱回収時に発生する酸性の凝縮水を機器内の中和器で処理し排出する仕組みとなっている。
解答:〇
解説:
排気ガス中の水蒸気には潜熱が含まれており、これを回収して給水を予熱することで熱効率を高めるのが潜熱回収型給湯機です。
潜熱回収の過程で酸性の凝縮水(ドレン水)が発生するため、中和器で処理してから排水します。
エネルギーの再利用と環境配慮の両立を目的とした設備です。
一級建築士試験(H30)環境・設備
デシカント空調方式は、除湿剤等を用いることにより潜熱を効率よく除去することが可能であり、潜熱と顕熱とを分離処理する空調システムに利用することができる。
解答:〇
解説:
デシカント空調は、吸湿剤を利用して空気中の水分(潜熱)を取り除く方式です。
これにより潜熱と顕熱を分離して制御でき、再熱や過冷却を抑えた高効率な除湿が可能になります。
近年では、オフィスや商業施設など湿度管理が重要な空間で活用が進んでいます。
試験対策のポイント
- 顕熱=温度変化、潜熱=湿度変化(蒸発・凝縮)と整理しておく
- 「人体」「空調」「設備機器」など、熱の出入りを扱う問題で頻出
- デシカント空調・潜熱回収機器など、新技術にも注目
暮らしへの応用|お風呂上がりに寒くなるのは“潜熱”のせい

お風呂上がりに、まだ体が温まっているはずなのに、急に「寒っ」と感じることはありませんか?
実はその原因は、“気化熱(きかねつ)”という潜熱の働きにあります。
水分が蒸発するとき、熱が奪われる
お風呂上がりに寒く感じるのは、肌に残った水分が蒸発する際に熱を奪うためです。
液体の水が気体(=水蒸気)へと変化する際には、「状態変化」に必要なエネルギーとして体の熱が使われます。これが気化熱であり、潜熱の一種です。
温度計上では大きな変化がなくても、体から熱エネルギーが奪われるために“冷たく”感じるのです。
つまり、これは「温度変化」ではなく「状態変化」によって熱が移動する典型的な例といえます。
だからこそ、お風呂上がりには早めにバスタオルで水分を拭き取ることが大切。
気化熱による体温低下を防ぎ、湯冷めを予防できます。
除湿機やエアコンも同じ原理
実は、除湿機やエアコンの「除湿モード」も、この潜熱のやりとりを応用しています。
空気を冷やすことで空気中の水蒸気を凝結させ、潜熱を放出させて湿度を下げるという仕組みです。
これにより、室内の湿度を下げながらも、温度を必要以上に下げずに快適さを保つことができます。
たとえば梅雨時期に「エアコンの除湿モードが一番快適」と感じるのは、温度よりも湿度(=潜熱)のコントロールが人の快適感に大きく影響しているからなのです。
建築知識が“暮らしの感覚”につながる
このように、建築環境で学ぶ「潜熱」「顕熱」といった概念は、実は私たちの日常生活の中にも深く関係しています。
お風呂上がりの寒さや、エアコンの快適さ──
その背景には、見えない熱の移動=エネルギーの流れがあります。
建築の知識を知ることで、暮らしの小さな「なぜ?」が解けていく。
そんな瞬間に、学びと生活がつながる面白さを感じられます。
まとめ|今日から“熱”の見え方が変わる
今回取り上げた「潜熱」は、建築環境分野の基本的な熱の概念のひとつです。
一見、試験のための専門用語のように感じますが、実は私たちの身のまわりのあらゆる“快適さ”と深く関わっています。
- 潜熱とは、状態変化に伴って出入りする熱エネルギーのこと。
(例:水が蒸発するとき、熱を奪って気化する=気化熱) - 人体の発熱・冷却や空調設備の除湿など、生活の中で常に働いている。
- 温度計に現れない“見えない熱”を理解することで、快適さを設計できる。
たとえば、お風呂上がりに感じる寒さ、梅雨時の除湿モードの快適さ──
そのどれもが、潜熱という“目に見えないエネルギーの移動”によって生まれています。
建築を学ぶことは、単に構造や法規を覚えることではなく、
「人の感じ方」や「暮らしの質」を支える仕組みを理解すること。
そうした視点を持つことで、知識が試験対策を超えて、日々の暮らしそのものに生きてきます。
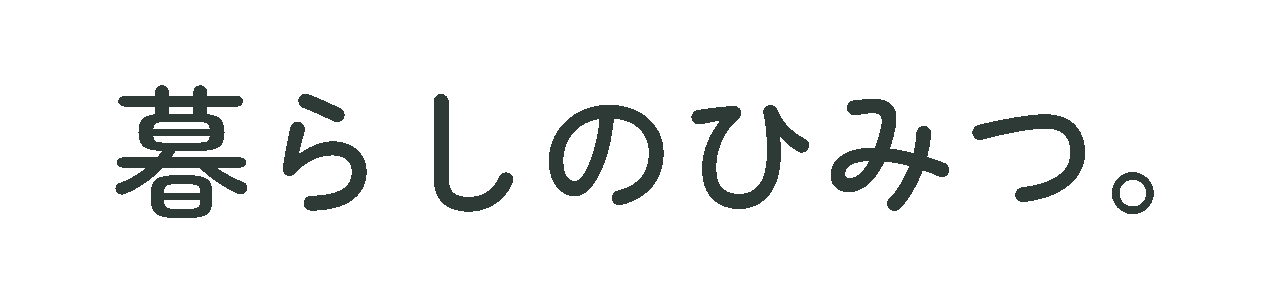

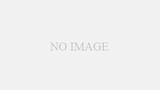
コメント